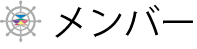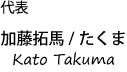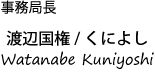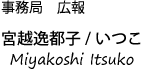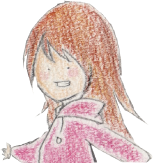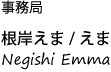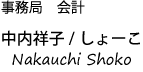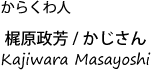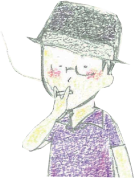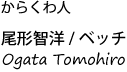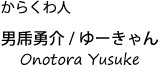???????????
????????????????????????????????????????
??????????????
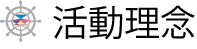
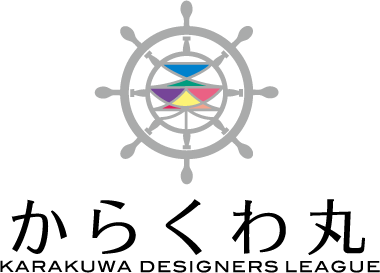
??????? ??????
????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????
???????????????????
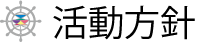
???????????????????????3????????????????????
 ???????????????????
???????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????
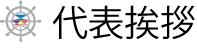
??????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????
??????? ??????????????????????????? ?????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????????
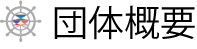




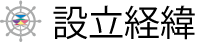
??????????????????????????
2011?3?24????????????FIWC?Friends International Work Camp?????????
?FIWC???????????
????????????????????????????????????????????
2011????????????????????????????????????????????
???2012????????????????????????????????????????????
????1????????????????????FIWC??????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????2012?5?10????????????????